会長挨拶
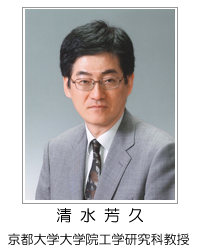 環境の毒性物質等によるリスク評価には、暴露量の予測や対象となる個々の化学物質の環境中の挙動や動態、消長を予測するモデルが必要です。また、毒性影響のためには、個々の物質の生物への影響に関するデータが必要です。
私が生物試験方法と出会ってから30年以上が経ちましたが、環境動態モデルはGISやリモートセンシング等の技術が発達してきましたし、個々の化学物質の生物影響は水系陸系合わせて全部で33種を数えてます(OECDガイドイラン)。
今後はこれらの生物試験技術が更に発展し、データの蓄積や法整備等を促し、日本に適合した総合的リスク評価手法を開発しなければなりません。そのうえで複合影響や毒性影響等を考慮したよりユーザーフレンドリーなリスク評価ツールも求めれています。
これからの日本のインフラや科学技術は、従来のような機能障害を起こさないことを前提にするのではなく、ひとつ機能が動作しなくなった時に他の方法で補完するシステムや、回復力を考慮したシステム構築が必要です。よく使われる「想定外」という言葉は、ある種の逃げかもしれません。
このように考えると、水処理技術がここまで進歩した日本では、本研究会が考究するWETは重要な意味を持つと思います。
環境の毒性物質等によるリスク評価には、暴露量の予測や対象となる個々の化学物質の環境中の挙動や動態、消長を予測するモデルが必要です。また、毒性影響のためには、個々の物質の生物への影響に関するデータが必要です。
私が生物試験方法と出会ってから30年以上が経ちましたが、環境動態モデルはGISやリモートセンシング等の技術が発達してきましたし、個々の化学物質の生物影響は水系陸系合わせて全部で33種を数えてます(OECDガイドイラン)。
今後はこれらの生物試験技術が更に発展し、データの蓄積や法整備等を促し、日本に適合した総合的リスク評価手法を開発しなければなりません。そのうえで複合影響や毒性影響等を考慮したよりユーザーフレンドリーなリスク評価ツールも求めれています。
これからの日本のインフラや科学技術は、従来のような機能障害を起こさないことを前提にするのではなく、ひとつ機能が動作しなくなった時に他の方法で補完するシステムや、回復力を考慮したシステム構築が必要です。よく使われる「想定外」という言葉は、ある種の逃げかもしれません。
このように考えると、水処理技術がここまで進歩した日本では、本研究会が考究するWETは重要な意味を持つと思います。
研究会設立目的
WET(Whole Effluent Toxicity)、すなわち全排水毒性評価を活用した新たな排水管理手法が環境省を中心に、導入の検討が開始されています。
これまでの日本国内の排水規制は、特定物質を個別に管理・規制するものです。しかし、国内で流通している化学物質は20000種を越え、これら物質を個別に規制するのはほぼ不可能であること、またそれぞれの化学物質の複合効果についての評価も非常に困難であると言わざるを得ません。 WETは、こうした従来の排水規制の欠点を補完し、バイオアッセイにより排水などに含まれる多種多様な化学物質の複合影響を総合的に捉え、原因物質が判明しなくても対策を行える点が特徴であります。WETは、すでに多くの国で実用化されており、日本でも対応が待たれていたところであります。 WETでは、毒性評価、毒性物質同定や、改善、継続的フォローアップなど、多くの課題が考えられます。
そこで、本研究会は各分野における企業および研究者が集合し、コラボレーションすることが有益であると判断し、生物学・バイオアッセイ、処理プロセス技術、 処理プロセス管理技術はじめ、最終的な総合マネジメント技術などについて研究・開発するOPENな会となっています。多くの知恵や技術を組み合わせることにより、効果的・効率的な実用システムを実現し、WET手法の具現化に寄与することができるものと考えております。
2011年5月27日都内において設立総会を開催し、具体的な研究活動を開始いたしました。
会員企業リスト・会員募集案内
| 会長 | 京都大学大学院工学研究科 教授 清水芳久 |
|---|---|
| 特別顧問 | 徳島大学総合科学部 准教授 山本裕史 |
| 理事 | JFEテクノリサーチ株式会社 株式会社日水コン 株式会社アクト 株式会社グローバル環境ソリューション 株式会社環境バイオ 株式会社正興電機製作所 |
| 会員 | 株式会社LSIメディエンス 三浦工業株式会社 化工機プラント環境エンジ株式会社 |
| 事務局 | 株式会社日水コン |
国内外を問わずメンバーを募集中です。本研究会の会則をご一読いただきご賛同いただけるのであれば、ぜひ事務局までご連絡ください。
主たる募集分野は以下の通りです。
- 生物学、バイオアッセイ技術(試験、分析)、毒物学
- 処理プロセス技術(分析、評価、改善、設計、施工)
- 処理プロセス運転管理技術(分析、評価、改善)
- フォローアップ(監視、オートセンター)
- 総合マネジメント技術
